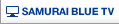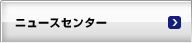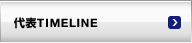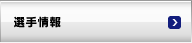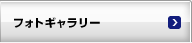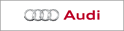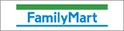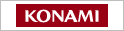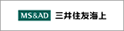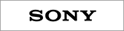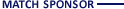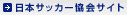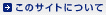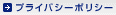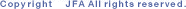ワールドカップがもたらす変化
「変化ねぇ…。うーん、どうかなぁ…」
ワールドカップ・南アフリカ大会で試合会場の1つになったケープタウンでサッカースクールを開いているクレイグ・ヘップバーンさんは、そう言って首をひねった。
大会も終わりに近づいた頃、ワールドカップ開催で、彼のアフリカン・ブラザース・アカデミーというスクールに通う子供たちや運営に何か変化はあったかと訊いてみた時のことだ。
彼のスクールには、テーブルマウンテンの麓に近い住宅街の一画を通りかかったときに、子供たちがボールを蹴っているのが目に停まって、立ち寄らせてもらった。南アフリカをはじめとするアフリカの子供たちにサッカーを広めようという始めた活動は、今年で14年目になるといい、この場所以外にもタウンシップでもスクールを開いているという。
オランダ対ウルグアイの準決勝第1戦が地元のグリーンポイントスタジアムで行われた翌日の7月7日、良く晴れた青空の下で、日本で言えば小学校の低~中学年くらいの子供たちが、10人ほどシュート練習に励んでいた。
黒人やカラードが多いが、中には、快進撃を続けているオランダのファンか、オレンジ色のシャツに身を包んだ白人の子供もいる。肌の色は違っても、どの子も実に楽しそうに何度もプレーを繰り返していた。
「サッカーには文化も人種の違いもない。子供たちはサッカーを通していろいろな世界とつながることができる」とクレイグさんは話す。
現在、常時スクールに通う子供たちは白人8人を含む35人ほど。モザンビークなど南アフリカ以外にも活動を広げているが、多くの場合、スクール開校はグランドの確保と荒地の整備から始まるという。
学校跡地を利用したケープタウンのこのグランドも、現在でこそ柔らかそうな草に覆われているが、かつては背の高い草に覆われた荒地で、ロッカールームに利用している建屋も、浮浪者が寝泊まりし、「衛生的にとてもひどい状態」だったとクレイグさんは振り返る。そこを、文字通り自分たちで清掃し整備を重ねて、サッカーができる場所を確保した。シューズやボール、ビブスやマーカーなど、トレーニングに必要な用具や、設備の修理に必要な道具は、活動に賛同してくれる企業や理解者の寄付や物品提供で賄ってきた。
南アフリカでは長い間続いたアパルトヘイト政策の影響で、肌の色によって教育の場も、生活の場も分けられてきた。白人の子供たちは、学校でラグビーやクリケットとともにサッカーも教えられないわけではないが、黒人が多く好んでプレーしてきたサッカーは、白人には観戦の機会もなければ、学校以外で活動の機会もなかったという。それが自然と、白人はラグビー、黒人はサッカーという大きな区分けを生んだというのだ。だが、スポーツだけでなく、多くの障害と問題をもたらすことになった人種隔離政策に終止符が打たれたのが1991年。わずかに、20年前のことにすぎない。
「南アと日本は共通点があると思っている。日本の第2次世界大戦後の短期間での復興の素晴らしさを見たら、アパルトヘイト政策があった南アも、日本から学べることあるんじゃないか、とね。僕らは日本のサッカー事情やアカデミーや指導のことを知りたいと考えているんだが、日本の人たちは僕たちの活動には興味はないだろうか」。
ワールドカップを開催し、できるだけ速やかに国際社会での地位を築きたいと願うのは、この国の経済だけではない。日本の戦後復興に、サッカーでもこの国の発展を重ねて可能性を探りたいと考えるのは、無理もないことかもしれない。
彼のスクールを手伝うコーチの一人のディノさんは、「子供たちが、どんどんプレー出来るようになるのを見るのは楽しいよ」と話す。
モザンビーク出身の若干20歳の黒人青年は、毎朝、子供たちに教えている。最年少は2歳半だという。彼自身も、以前はモザンビークの2部でプレーしていたが、教える楽しさに気付いたのだという。
「最初はFWだったんだけど、どんどん後ろに下がっていって最後はDFだった。後ろから仲間にコーチングするのが好きだったんだ。で、コーチになろうと思ったんだ」と言って笑った。
クレイグさんたちは、今後は施設を充実させて、サッカーだけでなく、子供たちが空き時間に宿題などの勉強ができる場所を提供しようと計画中だという。
教育の普及はこの国が抱える大きな問題の一つだ。世界的に悪名が高い犯罪率の高さに直結している。アパルトヘイト政策が生みだした大きなしわ寄せの一つだ。ワールドカップ大会の地元中継局のSABCも、“1 GOAL”というキャッチフレーズで展開している教育基金への参加を呼び掛け、大会中にはキャスターがキャンペーンTシャツを着るなど、多くのPRを展開していた。
サッカースクールの場を活用して、サッカーだけでなく、勉学にも親しめる機会を設けようという試みは、小規模ではあるが、この国を少しずつ変えて行こうという、彼らの熱意の表れでもある。
そういう話を熱く語ってくれていた時に、クレイグさんの携帯が鳴った。
「白人の家庭の御子さんが、ワールドカップをみてサッカーを始めたくなったから、スクールに入れないかって」。電話を切ったクレイグさんがそう教えてくれた。
変化は、少しずつ起きているのかもしれない。
Text by Kumi Kinohara